フアン・バレーラ(1824-1905)によるこの作品(1874)は19世紀スペインにおける最もポピュラーな小説とされています。作者は外交官兼政治家で数か国語に通じ、古典文学の原典とあらゆる土地の人間に関する豊富な知識を身につけていたといわれます。当時としては珍しい、純粋に心理的な作品です。
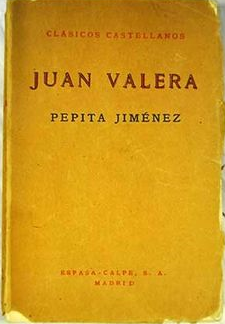
一人の神学生が若い未亡人に恋をして、その恋と戦い、ついに敗けて、けっきょく勝ち誇った美しい女性と結婚することになります。叔父の司祭にあてた一連の手紙のなかで、自分の心情をありのままに述べていますが、それがほぼ小説全体を構成しています。波瀾も筋もあってないような、しかし精巧きわまる心理解剖に満ちた作品です。その文体がまた魅力のひとつで、この作品を精読すればスペイン語の修行にも大いに役立ちそうな気がします。なお、これは当時のオペラや映画にもなったそうで、概要は以下のとおりです。
神学生のルイスは幼いころ司祭である叔父のもとに預けられ、神父への道を歩んでいましたが、叙任をまえに12年ぶりに休暇でアンダルシーアの実家に戻ります。父親のペドロは大農園主で村の有力者。55才ですが、男ぶりのよいドンフアンです。この村でも名の知れた美人ペピータ・ヒメネスに彼が言い寄っていることは周知のことでした。ルイスは早く司祭の叔父のもとに戻りたいと思いますが、父親があと2か月は留まるようにと彼を放しません。
ある日、ペピータ宅での宴会で初めて彼女を知ります。彼女は未だ20才そこそこですが、老齢の伯父との婚姻を余儀なくされ、3年後に未亡人となったこと、そして彼女の魅力的な容姿、聖人のような敬虔さなどを知り、父親の結婚相手として理想的だと考えます。父親に言わせると、ルイスは叔父から神学ばかり教えられ、世の中のことはなにも知らないとのことで、彼に馬術、カジノ、その他いろいろ教え込みます。その後ペピータ宅での会合にも参加したり、野外をいっしょに散歩したりするうちに、彼の心は罪深いと知りつつも次第にペピータへの情熱に傾斜していきます。そして神をも父をも裏切る罪深さに苦悩します。
その苦境から逃れるため、彼は司祭である叔父のもとへ戻ろうとしますが、ペピータは病気を装い、彼を枕元に呼び寄せ、道理にかなった説得を試みます。遂にルイスは聖職者になる道を諦め、ペピータへの愛を貫く意志を固め、父親に真実を話すことにします。彼が恐れたのはペピータへの愛を告白すれば父親がどう反応するかということでしたが、父親はすでに一切を承知し、理解している、自分もそういう結末に至るよう陰でできる限りの応援をしたのだよ、と明かします。
ルイスは幸福感に浸りながらも、幼い頃から夢にみた、自己を犠牲にして神に捧げるという理想を裏切ったことを忘れません。時折、いまの生活は俗悪で利己的だと思わないこともありません。しかしそういう時にはペピータが寄り添い、彼の憂いを晴らしてくれます。人はいかなる状態ないし条件のもとでも神に奉仕することは可能ではないか、また神を信じ愛することとこの世の愛を両立させることは可能ではないかと考えるに至ります。二人は現在の幸福に感謝しつつ、すべては神のお蔭であると考えます。

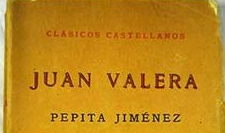
コメント