今年(2023年)はホルヘ・ルイス・ボルヘスの最初の著作『ブエノスアイレスの熱狂』(Fervor de Buenos Aires)が世に出てから、ちょうど100周年に当たります。同書は父親ホルヘ・ギジェルモの援助で、300部が自費出版された由。ボルヘスの自伝によれば、そのうちの50部から100部を当時の有名な文学雑誌の編集長に託し、訪問客のポケットに同書をねじ込んでもらったとか。ボルヘスは遺伝性疾患により若くして視力を失い、その後盲目同然となったこともあり、両親から愛され、母親ドニャ・レオノールは自身が99才で亡くなるまでボルヘスの面倒を見たと聞きます。また、父親は「哲学的無政府主義者」と呼ばれ、ボルヘスは父親の文学的血筋を受け継いだようです。
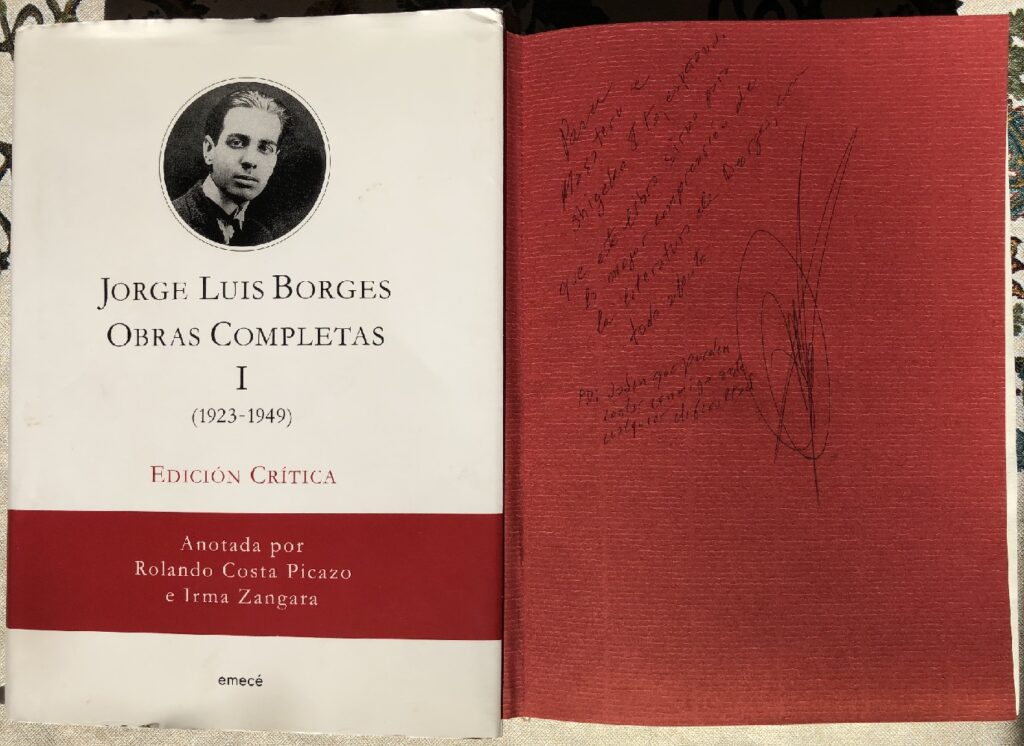
「ブエノスアイレスの熱狂」は46篇の詩から成りますが、そのうちのいくつかを拾ってご紹介します。
最初の詩は「街路」<<Las calles>>。ブエノスアイレスの寂しい「街路」はボルヘスにとって心の拠りどころであったようです。「ブエノスアイレスの街路は自分の心の故郷だ」といいます。この街を一つの都市というより一つの祖国のように感じていたようです。
次の「ラ・レコレッタ」<<La Recoleta>>では、まだ二十才を過ぎたばかりのボルヘスが、祖先の眠る墓地を眺めながら、いずれ自分もここに眠ることになると思い、死について考えます。霊魂が尽きると時間も空間も死も無くなるであろう、と。
「見知らぬ通り」<<Calle desconocida >>では、日が暮れた通りはどの家も燭台のようで、人々の命も孤立したろうそくのよう。そしてわれわれの足取りはすべてゴルゴタの丘に向かって歩んでいるように見える、、、
「サン・マルティン広場」<<La plaza San Martín >>では、「落ち着いた、味わい深い広場」、夜の「青」と土の「赤」、また「魂を等しくさせる深い広場が死のごとく、夢のごとく開ける」と歌います。
「墓碑名」<<Inscripción sepulcral>>と題する曾祖父に捧げられた短い詩では、軍を率いてアンデス越えを果たし、ペルーの独立に尽くした軍人、曾祖父を称えます。
「年の暮」<<Final de año>>では、時間の謎について思いを巡らせます。われわれはヘラクレイトスの「同じ河に二度入ることはできない」という流れの一滴に過ぎないが、それでも我々のなかに何かが残るのはないか、と。
「街外れ」<<Arrabal>>では、「この都は自分の過去と感じていた /この都は自分の未来であり、現在である / ヨーロッパに住んだ年月は幻に過ぎない / 自分はいつもブエノスアイレスにいた、そしてこれからも」 などと歌います。
この詩集の出版100周年記念行事はブエノスアイレスではすでに行われ、マドリードでも未亡人マリア・コダマ女史の立ち合いのもと行われる予定でした。


コメント