アソリン(ホセ・マルティネス・ルイス)は繊細かつ綿密な作家で、ありふれたものに特別な愛着を抱き、大げさなことは軽蔑する人のようです。彼は人生のはかなさ、死の速やかさについて鋭敏な感覚をもち、このはかない人生を、実に純潔な表現で、こと細かく描くことによって引き留めようとするかのようです。また、修辞学の大家で、スペイン語に特別の愛着を抱いていることが伺われます。

この『田舎の町々』は20世紀初頭におけるスペインの田舎の自然や人々の暮らしを詩的な散文で描写した20篇近くの随筆で、最後は「悲劇的なアンダルシア」で終わります。ここでは最初の3篇と最後の1篇を紹介したいと思います。
お祭り
年老いた詩人ドン・ホアキンが20年ぶりに故郷の祭りの日に戻ってくる。村人たちとあいさつを交わすが、目が不自由で、相手の顔も判別できない。遠くから鐘の音が聞こえてくる。セミも鳴いている。しかし夏が終わるとセミは死んでしまう。我々詩人も、歌える限り歌うが、冬が、すなわち老いが訪れると、忘れ去られ、死んでいくのだろう。花火が上がり、行列が近づいてくる。幼い子供たちが踊りながら通り過ぎていく。
サリオ
青少年時代を過ごした村を何年ぶりかに訪れ、旧友のサリオに会いに行く。家の扉が半開きになっているが、呼んでも誰も出てこない。手を叩いたり、叫んだりしても答えがないので嫌な予感がする。さらに大きく手を叩くうちに、ようやく男の子が現れる。サリオは、と訊くと寝ているという。彼は朝3時に起き、その後また床につくとのこと。カルメンは、と訊くと、嫁に行ったという。ロラは、と尋ねると、彼女も結婚したという。ペピタは、と問うと、彼女は亡くなった、と。そのうちに足音が聞こえ、サリオが足を引きずりながら現れる。いつもきれいに髭をそっていた彼が長い無精ひげを生やしている。いつもアイロン掛けしたばかりのシャツを着ていた彼が、よれよれのシャツで、手摺につかまりながら階段を降りてくる。サリオがぼーっとしているので、「サリオ!サリオ!」と叫ぶと、やっと、「あー、アソリン、、、」と言う。その後、また長い沈黙が続く。
彼と別れて街路に出ると、小川のせせらぎも、空を飛ぶ鳥の鳴き声も、古い時計台の鐘の音も、あたかも人間の苦悩とは関わりないという風だ。
セルバンテスの婚約者
汽車でひとり旅をする作者は乗り合わせた幼い子供たちとともに歌ったりしている。そのうち、”イエレス!一分停車!“ のアナウンスを耳にして慌てて下車。駅に人影はない。夜の9時。エスキビアスまで1時間かかるそうだが、この時間には乗り物もない。とぼとぼ歩いていると犬の鳴き声が聞こえ、ようやくエスキビアスに着く。そこで宿屋を兼ねた飲み屋が見つかる。この町はセルバンテスとカタリナが新婚生活を始めたところだ。翌朝あちこち歩くうちに「カタリナ通り」と「セルバンテス広場」があり、セルバンテスの家が見つかる。中を案内してくれた女性が若くて、美しく、まさにカタリナを彷彿させる。
悲劇的なアンダルシア
汽車の窓から永らくラ・マンチャの荒涼とした風景を目にした後、作者は夜明けにロラ・デル・リオとブレネスを経てセビーリャに到着。アンダルシア訛りの賑やかな声があちこちから聞こえる。大聖堂とヒラルダの塔の傍で語り合っている若者たちは、セルバンテス模範小説集の『犬の会話』に登場する屠殺人を思わせる。そこからレブリハへ向かう。ここは村中が静まり返り、叫び声も、物音も、歌声も聞こえない。カジノを覗くと、人っ子一人いない。干ばつで畑がやられ、農民はみんな飢えているという。医者に訊くと、この地方の労働者はいずれも栄養不良のため貧血を患い、それが肺結核を引き起こしており、死亡率が急速に増えているという。この地が飢えと貧困のどん底にあることを知って愕然とする。そしてなんらかの革命的措置の必要性を痛感する。

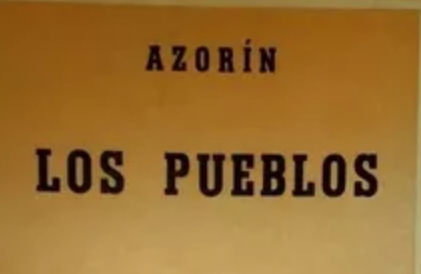
コメント