アレハンドロ・カソーナ(1903-75)はスペインの劇作家兼詩人で、この作品は1949年に発表され、アルゼンチンやスペインで上演されたようです。原題の直訳は『木々は立ったまま枯れる』で、同作家による『われらのナターチャ』も有名です。この作品の主人公ともいえる祖母は、現実と夢を比べ、皆の幸せのため現実よりも夢を選ぶという物語です。心のうちは死んだも同然だが、形のうえでは立っている木々のようだと語ります。
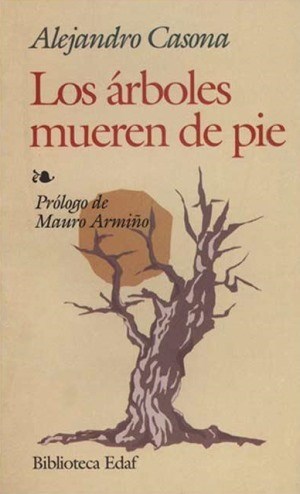
第1幕
バルボア一家はもともと幸せな大家族であったが、今では祖父のバルボアと祖母、そして孫の3人のみが残された。祖父母は残った唯一の家族である孫を大事に育てるが、あまりにも甘やかし過ぎたせいか、そのうち彼はしばしば外泊し、賭けごとで借金をつくり、遂には犯罪に手を染めるようになった。忠告すると、祖父に暴力すら振るう始末で、たまりかねた祖父は彼を家から追い出した。
孫を愛する祖母は一言も異を唱えなかったが、そのうちにみるみる落ち込み、日ごとに弱っていく。それを見かねた祖父は、祖母のために孫の手紙を偽造し始める。孫の手紙はカナダ発でそれに祖母が返事を書き、2~3ヶ月ごとの手紙のやりとりが始まった。孫の手紙には、モントリオール大学を卒業したとか、そりで森や湖を旅したとか、建築士になるための勉強を始めたとか、そして美しい女性と恋仲になり、彼女と結婚した、等々が認められていた。
ところがある日、突然電報が届き、孫は1週間後に船で到着するとのこと、祖母は20年ぶりに孫に会えると大喜びする。
第2幕
孫は実家を訪れ、現金をせびろうとしていたようだが、報道によると乗船したはずの船は沖合で難破したらしい。祖父のバルボアは祖母を悲しませないため、それは知らせず、ある慈善団体に依頼し、実の孫の代わりに孫とその妻の役を演ずる男女を提供してもらうことにする。マウリシオが孫役、イサベルが孫の妻役に扮し、二人は祖母と実に仲むつまじい関係を築く。祖母はウソに気づいてはいたが、それは内に仕舞いこみ、幸せな日々に感謝していた。
第3幕
ところがある夜遅く、実の孫が家にやってきた。祖父は驚くが、孫は、自分は事故に遭ったあの船には乗っていない、施しを乞いに帰宅したのではなく、両親の遺産の分け前20万ペソを受け取るために来たのだと言う。彼は祖母を頼りにしており、祖父はなにも知らない祖母に会わせてはならないと抵抗するが、結局孫は祖母とも対面することとなる。しかし祖母は、いま一緒に住んでいる明るくて真面目な子ではなく、この哀れなならず者を自分の孫として認めることができないと、遂に彼の要求を拒絶する。
孫はマウリシオに促され、家を去っていく。

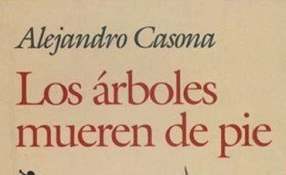
コメント