フランシスコ・デ・ケベード(1580-1645)は、スペイン文化の黄金時代を代表する作家、詩人で、この作品はいわゆる “ピカレスク小説” に属します。ピカレスク小説は日本では一般に “悪者(ないし悪漢)小説 “ と訳されていますが、スペイン王室アカデミー辞典によれば、 ピカロは「悪賢く、才知あふれ、いかがわしい生活をしている下層階級の者」と定義されています。この作品は辛辣な風刺と、それにドン・キホーテのような機知とユーモアに富んでおり、40年前メキシコから休暇帰国した折に初めて読みました。そして8年前に再読、今回が3度目でした。
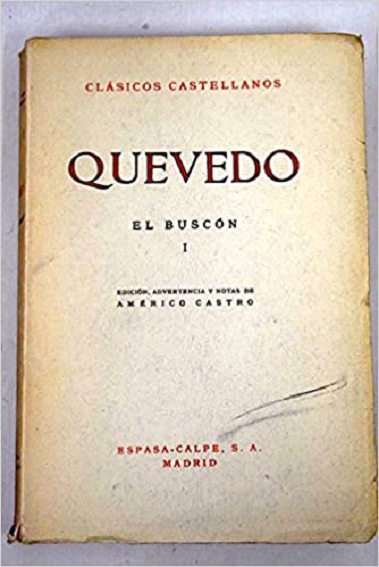
ケベードは恐るべき風刺作家で、言葉の天才的巨匠といえるでしょう。その激しくも魅力的な文体とともに、下層階級の隠語を含めきわめて多岐にわたる語彙のせいもあり、われわれ日本人にとって原文の読破は決して容易ではありません。
主人公ドン・パブロスはセゴビアの貧しい理髪師の子。学校に通い始めると、金持ちの子である友だちドン・ディエゴと親しくなり、一緒にとある学士宅に下宿しますが、碌な食事も与えられず、空腹で夜も眠れない。ガリガリに痩せ細り、医者がいうには、9日間彼らの部屋では大声でしゃべらないように、空っぽの胃に響くから、と。その後ドン・ディエゴがアルカラ市の上級校に進むと彼もお供する。スペイン特有の 学生寮内の新入生いじめに遭ったりし、以前の下宿以上の苦労もしますが、なんとか切り抜ける。そこで “郷に入っては郷に従え” の諺に倣い、悪党に対してはこちらも悪党になる決心をして、新たな人生を始めます。
豚を盗んだり、女主人から頼まれた買い物の値段をごまかして、吸血鬼のように金銭をかすめ取ることを覚える。女主人が鶏を ”ピオ、ピオ” と呼ぶので、ピオ教皇を侮辱する行為として宗教裁判にかけられるかも知れないよと脅し、2羽の鶏をせしめる。その他いろいろ悪知恵を働かすと、仲間から煽てられ、機知に富んだわんぱく小僧として名声を博します。そしてピカロとしてのプロの道を歩んでいく。
日本の古典に “ピカレスク小説” と似たジャンルは存在しませんが、強いて挙げれば井原西鶴の『世間胸算用』にやや共通点が見られるかも知れません。サブタイトルが「大晦日は一日千金」となっているとおり、江戸時代の大晦日の町人たちのさまざまな姿を描いた物語です。当時の商売は「掛け売り」が基本でした。そして、大晦日は一年の総決算の日。というわけで、この『世間胸算用』には、なんとかして長年のツケを取り戻そうと躍起になる借金取りや、どうにかしてやり過ごし、笑って正月を迎えようとする人々などなど。
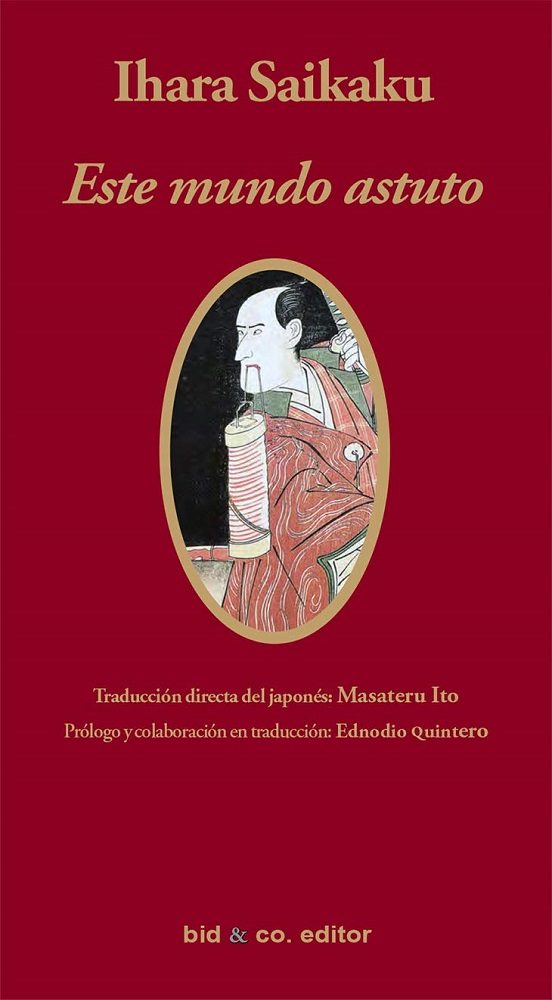
借金が多い人は、大晦日は、借金取りから逃れようと家を空けていることが多いものなのに、とある男は、なにごとか悟ったかのように自宅の庭で包丁を研いでいる。「こんな風に包丁のさびを落としたところで、さばくものといえば、子鰯(ごまめ)一匹ありはしないのだが、しかし、世の中、何があるかわからない、、、なにか急に腹の立つことでも起きて、自害する役に立つかもしれん、、、」などと、なにか憑かれたような目つきをして包丁を持って身構えていたところに大きな鶏が近づいてきた。「おのれ!死出での門出に!」男は一言いうと、鶏の首を一気に斬り落とした!この様子を見ていた何人もの借金取りは、一人、また一人と男の家を後にしたという。
『世間胸算用』には借金取りの話だけではなく、さまざまな町人の姿が描かれ、面白い話が満載で、スペインのピカレスク小説を思い出させてくれます。 (了)

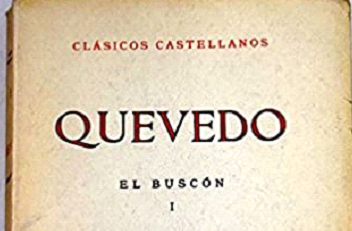
コメント