最近、スペインの劇作家カルデロン・デ・ラ・バルカ(1600-1681)の戯曲『人生は夢』を再読しました。スペインの黄金世紀のみならず現代にいたる全ヨーロッパ演劇中の傑作とされ、バロック演劇の典型ともいわれる哲学的作品です。
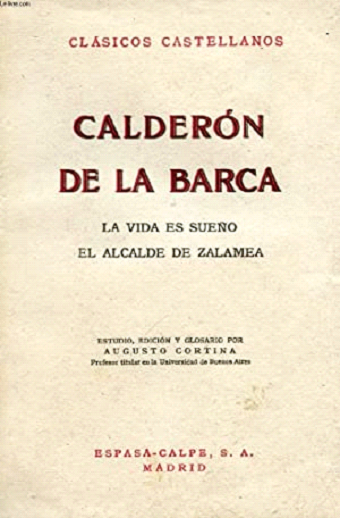
ポロニア王バシリオはわが子(セヒスムンド)誕生の折、星占いでいずれ王座を息子に奪われるとのお告げをうけ、彼を険しい山中の洞窟に幽閉します。しかし王子の成長後、思い直した王は、わが子が予測したとおり残忍無惨な王子、神をも恐れぬ王となって国土を滅ぼすのか、それとも己の運命を克服し、めでたく国を治める王となるのかを試すため、薬を使って王子を眠らせ、王宮へと連れ戻します。眠った状態で王子を連れ戻させたのは、もし目覚めてからの行状いかんによってすぐにでもまた元の洞窟へ連れ戻さざるを得なくなっても、一切が夢の中での出来事であったと思わせるためです。王宮で眠りから覚めた王子はこれまでのうっ憤もあり、残忍な振舞いに及びます。そのため再び薬で眠らされ、洞窟へ連れ戻されます。洞窟で再び眠りから覚めた王子は、王宮での一件はすべて夢の中での出来事であったと思い、こう述懐します。
<<人生とは何だ? / 狂気だ。/ 人生とは何だ? / まぼろしだ、/ 影だ、/ 見せかけだ、/ そして 大いなる幸せといえども取るに足らない、/ 人生はすべて夢なのだ、/ そして夢はしょせん夢でしかない。>>
王子セヒスムンドは実際に夢を見たわけではありませんが、王宮での出来事を彼は夢だと思ってしまいます。 さらに”夢から覚めた”いまの状況も、彼は夢であるとみなします。彼はいま”鎖につながれた夢を見ている” と言うのです。 薬によって眠らされたしばしの時間を境に、王宮での時間も、またいまの洞窟内での時間も、彼はどちらも夢であるとみなすのです。人の一生はまさに夢、人生は夢の連続である、と。 第3幕に至り、セヒスムンドはもう一度洞窟を出ることになります。異国人を跡継ぎに据えようとする父国王に謀叛しようという兵士たちに祭り上げられ、セヒスムンドは話に乗ります。
<<人生は短い / よし、それならもう一度 / 夢を見てやろうではないか / ただしよく弁(わきま)え、よく心掛けておく必要がある、/ 楽しい夢は、夢を見ているその最中に / 目が覚めるものだということを。>>
セヒスムンドは、夢と覚悟の上で再び行動しますが、人生はどこまでも夢であると見切っています。 こうして父王バシリオと王子セヒスムンドの両軍が相対峙する。そして父王の軍の敗北。 しかし王子は驕ることなく父王に恭順の意を表し、父王は改めて王子に王位を譲ります。 大団円。 最後にセヒスムンドは言います。
<<かくしてわたしは悟るに至った / 人間の幸福はすべて / 結局は夢と消え去るということを / いまはこの幸福を / それが続くあいだ / 味わっていたいと思う / 自分たちの犯す過ちを赦してもらえるよう / 請い願いながら。>>
なお、セヒスムンドは、王宮での一件が夢ではなく現実の出来事であったことに気づいていたふしがあります。その上で彼は、夢の中のこととされることもまた現実のことも、すべて夢とみなします。すべてを夢のごとくはかないものであると見做すのです。
『人生は夢』は、生まれたままの人間は一種の野獣であって、ただ信仰に基づいた理性によってはじめて粗野な本性に打ち勝つことができるという思想を表現したものと言われます。理性にとってはすべてが夢であり、嘘である。彼岸の永遠の世界にしか真実はないという。
ところで、「人生は夢」という発想は古くから日本にもあります。室町小歌の珠玉を集めた『閑吟集』(1518)にこんな歌謡があります。
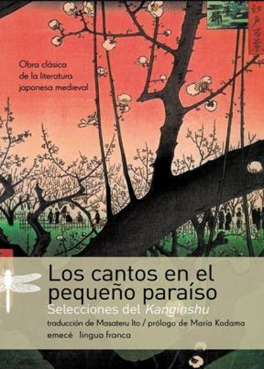
うき世
世間(よのなか)は、ちろりに過ぐる
ちろり、ちろり
何ともなやなう、何ともなやなう
うき世は風波(ふうは)の一葉(いちえふ)よ (49-50)ただ何ごともかごとも
夢まぼろしや水の泡
笹(ささ)の葉に置く露(つゆ)の間(ま)に
味気(あぢき)なの世や
夢まぼろしや、南無三宝(なむさんぼう)(52-53)くすむ人はみられぬ
夢の夢の、夢の世を、うつつ顔して
何せうぞ、くすんで
一期(いちご)は夢よ、ただ狂へ (54-55)
宗教には「悟り型」と「救い型」があるといわれます。悟り型というのは仏教に代表されるような、心と体を訓練して別の人格へ生まれ変わることを主眼にします。救い型はキリスト教などのように、神や超越的存在が救ってくれるという宗教です。近代になり、日本の知識人たちはキリスト教文化圏からの哲学・思想に触れました。そこには人は生まれながらに罪を背負っているという「原罪」の感覚が深く浸透しています。日本の思想や宗教には、あまりそうした性質のものはありませんが、親鸞(1173-1262)だけは別でした。

明治以降の思想家や哲学者たちは親鸞の教えを説いた『歎異抄』に、近代知性ともがっぷり四つに組める罪業観が備わっていることを見出したのです。親鸞の「善人なほもつて往生をとぐ。いはんや悪人をや」、すなわち「悪人正機説」です。ここでの「善人」は「自力で修めた善によって往生しようとする人」を意味します。そして「悪人」は「煩悩具足のわれら」を指しています。我々はどんな修行を実践しても迷いの世界から離れられません。阿弥陀仏は、それを憐れに思って本願を起こした、悪人を救うための仏だというわけです。 (了)

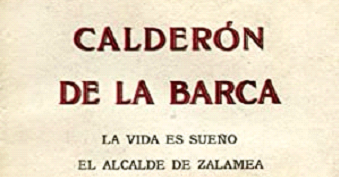
コメント