グスタボ・アドルフォ・ベッケル(1836-1870)はスペインの国民的詩人ですが、健康と家庭に恵まれず、不遇の生涯を送った末に夭逝しました。死後に唯一の詩集『抒情詩集』を遺し、スペイン近代詩の源流として高く評価され、後世の詩人に多大の影響を与えたといわれます。他方、スペインの各地の伝説等に題を採った幻想的短編集である『伝説集』も遺しています。ここではその『伝説集』 (Leyendas, 1871)のなかの3篇のみを紹介したいと思います。
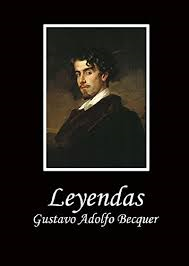
オルガン弾きペレス
セビリャのサンタ・イネス修道院の中庭でクリスマスイブ真夜中のミサを待つ間、修道院使用人が語るには、ここにはかつてペレスという名のオルガン弾きがいたという。彼は生まれつき盲目であったが、まるで聖人のようで、貧しいながらも物惜しみせず、家族は一人娘のみ、唯一の友はオルガンだったとのこと。オルガンは古びていたが、修理も自ら手探りでしていた。彼の弾くオルガンの音色はさながら天使の声のようで、大司教も彼のオルガンを聴くためにこの小さな教会に足を運んでいたほどであった。
ある年のクリスマスイブ、ミサの時刻になってもペレスが姿を見せないので出席者が動揺し始めると、一人の斜視男がペレスは病に伏しているので代わりに自分が弾こうと言い出した。しかし暫くすると、青ざめたペレスが医師の忠告も聞かずに姿を見せ、オルガンを弾き始める。しかしその音色は次第に弱まり、会場から娘の悲鳴が起こると、父親はオルガンにうつ伏せに倒れ、そのまま息を引き取った。
翌年のクリスマスイブにはオルガンは別の奏者に委ねられたが、彼は以後あのオルガンには触れたくないという。それからさらに1年が経ち、修道院長はペレスの娘にオルガンを弾かせようとする。しかし彼女はあのオルガンを弾くのは怖いと言う。そしてミサが始まり、いよいよオルガンを弾く瞬間になると、誰も触れないオルガンが独りでに、あたかも天使が弾いているように鳴り始めた。
緑色の瞳
アルメナル家の長男フェルナンドは、ある日、勢子のイニゴと猟に出かけ、首尾よく鹿を射とめるが、鹿は傷を負いながらも逃走する。そして悪霊が宿るといわれ、人が怖がって寄りつかない「アラモの泉」と呼ばれるところへ逃げ込んだ。フェルナンドも鹿を追ってその中へ入り込む。イニゴはその辺りは危険で、鹿はもう取り逃がしたと告げるが、フェルナンドは自分が初めて射とめた獲物を手に入れようと得意になって深く入り込んでいく。イニゴは思い止まらせようとするが、彼は耳を貸さない。
数日後、イニゴはフェルナンドに、「アラモの泉」へ行ってから顔色が悪く、いつもふさぎ込んでいるがどうしたのかと訊く。フェルナンドは、あの場所はすばらしく、岩の合間からえも言われぬ美しい「緑色の瞳」が見えた。自分はそのとりことなり、毎日その女性を探している、という。イニゴは恐れおののいた表情で、実はその女性は悪魔で、あなたの魂を奪おうとしているのだ、と告げる。
フェルナンドはそれには耳を貸さず、遂に泉のほとりで、その謎の女性と対面する。彼は妄想に取りつかれ、たとえ悪魔であろうとも彼女を永遠に愛するであろうと告白する。彼女は、自分は悪い女ではなく、自分も彼を愛していると告げる。結局、フェルナンドは女に口説き落とされ、雪のような冷たい接吻を受けながら、水中に引きずり込まれ、息絶える
月光
これはスペイン北部のソリア県に住み、孤独と詩を愛するマンリケという貴族の若者の物語である。
ある夜、修道院の廃墟を散歩していると、美しい女性を見かけたような気がしたので後を追うが、そのうち姿を見失ってしまう。その後、彼は自然の風景を眺めたり、独り言を呟いて過ごすことが多くなり、貴族の同僚たちは皆、彼は気がふれたのではないかといぶかるようになった。
ある夜、独りで森にいると、彼は幽霊を見たような気がする。そして、それは美しい女性であったと気づく。それから2か月にわたり、彼は愛しい彼女を探し求めてソリアの地をさまよう。しかし彼女の姿は見つからない。ところがある夜、なんと以前に彼女を目にしたと同じ場所で彼女を見つける。そして驚いたことに、彼の思い姫は他でもない月光に過ぎないことに気づいた。


コメント