ほぼ15年ぶりにこのロペの戯曲(1617年)を読み返しました。
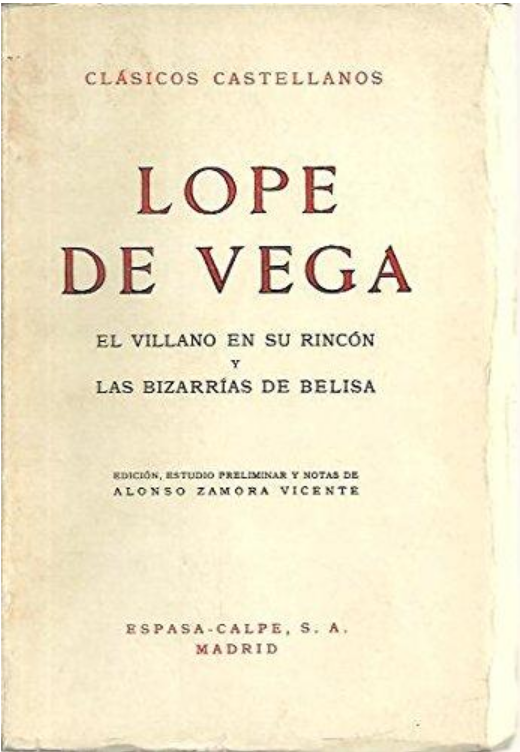
舞台はフランス。主人公は「農夫フアン」。農夫とはいえ、フアンは裕福な農園主で、首都パリ(王宮の所在地)からやや離れた静かな土地で、なに不自由なく、野心も抱かず、日々神に感謝しながら、悠々自適の生活を送っています。ある日、息子のフェリシアノは、国王が狩りに出かけ、途中この近くを通られるそうなので一目見に行かないかと誘いますが、父親は自分がこの地の片隅の王だと自負しているので、他の王に会いたいとは思わない、と答えます。娘のリサルダも兄フェリシアノと同じく、首都の生活に憧れており、彼女は最近宮廷の騎士オトンと知り合い、互いに心を惹かれています。
国王はその村を通るとき、教会の柱にこんな墓碑銘が刻まれているのに気づきます。
<<農夫フアンここに眠る / 主人に仕えたことも / 宮廷を見たことも、 国王に会ったこともなく / 恐れを抱いたことも、与えたこともなく / 困窮したことも / 怪我をしたことも、拘束されたこともなく / この歳に至るまで / 彼の家には不運も / 妬みも、病気もなかった。>>
好奇心に駆られた国王が村人たちに彼のことを尋ねると、彼は未だ存命とのこと。そして村人は皆彼について敬意と愛情を込めて語ります。 国王はフアンが羨ましくもあり、また国王に会いたくないのはなぜなのかを知りたく、ぜひ彼に会ってみたいと思います。
そこでイノシシ狩りを口実にフアンの家へ赴きます。フアンには道に迷った警備隊長を装って情けを乞います。突然の訪問客をフアンは丁重にもてなし、劇はクライマックスに。
夕食の席上、相手が国王であるとは夢にも思わないフアンは、国王に対する自分の忠誠心が他の誰にも劣らないことを誇りにしていること、もし国王から求められれば、自分の息子・娘でも、邸宅でも、金銭でも直ちに差し出す用意があること、なぜなら自分の生活のすべてが国王のお蔭であるから、しかし国王にお会いする気は毛頭なく、自分の幸福はこの片隅にひっそりと暮らすことにある、などと語ります。フアンの考え方が堅実、純粋で、分別のあることに改めて国王は羨ましく思います。夕食には歌の演奏があり、客人はその夜フアンの家で泊まります。
ある日、宮廷の騎士オトンが国王の書簡をもって村にやって来ます。国王がフアンに10万エスクードのお金を都合してほしいとのこと。フアンは躊躇なくそれを手渡し、必要とあれば財産や息子・娘も差し出す用意があることも付言します。するとまた国王の書簡が届き、娘リサルダと息子フェリシアノを宮廷に寄こすようにとのこと。リサルダに思いを寄せる騎士オトンは、国王への猜疑心と嫉妬心を抱きます。国王はフェリシアノを警備隊長に任命し、フアンにもぜひ宮廷に出仕するよう命じます。
フアンは宮廷で国王に会い、あの夜の訪問客は国王であったことに初めて気づきます。国王はフアンをテーブルの上座に座らせ、食事とともに音楽が始まります。先ず三つの皿が運ばれ、一つには権力の象徴としての笏(しゃく)、もう一つには家臣の鏡である王の象徴としての鏡、最後の一つには正義の象徴としての剣が置かれています。さらに別の3つの皿が運ばれ、一つにはフェリシアノに高位の貴族称号を授与する証書、もう一つには10万エスクードの持参金、そして3つ目には農夫フアンに内大臣の称号を与える旨の証書が載せられていました。そして最後にリサルダとオトンの結婚が認められ、国王と王女アナが付添い人になるという結末で幕が閉じられます。
あら筋だけを述べると素っ気ないですが、戯曲としてなかなか味わい深い作品です。
農夫フアンの生き様は、まさに禅宗でいう「無位の真人」(一切の枠や範疇を超えた自由人)の趣があります。
ドン・キホーテもサンチョ・パンサの生き方を羨んでおり、またロペが絶賛したフライ・ルイス・デ・レオン (1527- 1591) はこんな詩を残しています。
吾、己とともに生きん 然して天より授かりし恵みを楽しまん ただ独り、人目に煩わされることもなく 愛、妬み、憎しみ、 希望、不安から解き放たれて
果たして農夫フアンが、宮廷において、これまでの生き方を貫けるのかどうか、やや気になるところです。

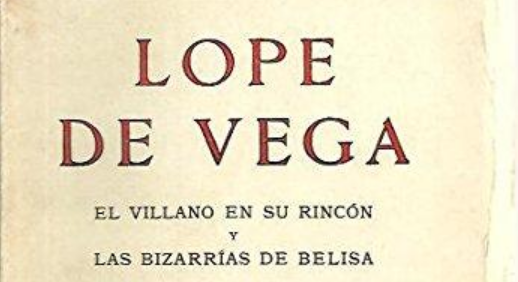
コメント